���̃T�C�g�ٌ͕�m�Ƃ̑��k���X���[�Y�ɍs���悤�Ɏx������T�C�g�ł��B
�@���ō����Ă�����͂��̃T�C�g�����Ă���
�ٌ�m�ɑ��k���܂��傤�B
�Y�̏d���̍l����
�Y�̏d���̍l����
�����@������T�C�g�@�g�b�v�y�[�W���Y�@���Y�̏d���̍l�����Y�@�ɂ��Y�̏d���ɂ��āA
�Y�̎�ށA���s�P�\�A�����߁A�Y�̖Ə��A�����ɂ���
�Y�̏d��������������e���܂߂ĉ�����Ă����܂��B
�X�|���T�[�h�����N
�Y�̎��
�Y�ɂ͏d�����ŁA�E���Y
�E����
�E����
�E����
�E�S��
�E�ȗ�
�E�v��
������܂��B
���Y
�Y���{�ݓ��ɂ����āA�i�܂��B
����
�Y���{�݂ɍS�u���ď���̍�Ƃ��s��܂��B
�S�����ē������邱�ƁB
����
�Y���{�݂ɍS�u���܂��B
�S�����邾���B
����
1���~�ȏ�̂������x�������ƁB
�������Ȃ��ꍇ�́A������܂ŋ����J���ɂȂ�B
�i�ő�2�N�Ԃ܂œ����j
�S��
1���ȏ�30�������ōS�����邱�ƁB
�ȗ�
1000�~�ȏ�1���~�����̂��������ƁB
�v��
�ƍߍs�ׂɎg��������
�ƍߍs�ׂŕs���ɓ�����V��Ή���v�����܂��B
��̂̔ƍ߂͒������N�Ƃ������̂������ł��傤�B
����̓j���[�X���Ă��Ă�
��̂��������N�ƌ����Ă��邱�Ƃ�����킩��܂��B
���s�P�\
��ʓI�ɂЂǂ��ƍ߂ɑ��Ă��u���s�P�\�Ȃ�Ă����ɁA���Y�ɂ���I�v
�Ƃ��悭�ᔻ�������܂����A
���s�P�\�Ƃ͂ǂ��������Ƃł��傤���B
���s�P�\�Ƃ́A
�E3�N�ȉ��̒���
�E50���~�ȉ��̔���
�̂����ꂩ�̔����������n���ꂽ�Ƃ��ɁA
�ȑO�ɋ����ȏ�̌Y�ɂȂ��Ă��Ȃ��l�́A
���ޗʂ�����A1�`5�N�̌Y�̎��s��P�\���Ă��炦�܂��B
�P�\���Ă̂́u�҂��Ă����v�Ƃ������Ƃł��B
�܂�A
�u�ȑO�ɑ傫�Ȕƍ߂��������Ƃ������l�ŁA
���ޗʂ�����ő�5�N�̊ԁA�Y�����ɓ���Ȃ��v
�Ƃ������Ƃł��B
���s�P�\���Ԓ��ɐg�ӂ����āA
�S�̏��������ČY�����ɕ������邱�Ƃ��o���܂��B
�܂�A���s�P�\�����Ƃ������Ƃ�
�Y�͌y���Ȃ�Ȃ����ǁA
1�̌Y�̌y���Ƃ����`�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�s���̔��f�ɂ���ẮA
�ی�ώ@�Ƃ����Ď��҂���������ԂŎ��s�P�\���܂��B
���s�P�\���Ԓ��ɂ܂��߂�Ƃ����ꍇ�́A
���s�P�\�͎������ɂȂ�܂��B
������
�����߂Ƃ́A2�̍߂��ɋN�������ꍇ���ǂ�������舵���ɂȂ邩�Ƃ������̂ł��B
��
�l�̉ƂɐN�����A���i��D�����B
�l�̉ƂɐN�����Z���N����
���i��D�����ޓ���
�Z���N���߂Ɛޓ��߂̗����̌Y��
�Ȃ����Ƃ��̂��Ƃ��߂ƌ����܂��B
1�̌Y�����Y�Ȃ�A���̌Y���Ȃ��Ȃ��B
1�̌Y���������͖��������Ȃ�A���̌Y���Ȃ��Ȃ��B
�L�������́A�ł��d���߂̌Y���̒����̔����̊��Ԃ��v���X����B
�S���A�����A�ȗ��Ƒ��̌Y�́A�����Ȃ���܂��B
1�̍s�ׂ�2�ȏ�̔ƍ߂ɊY���������́A
���̒��̌Y�̍ł��d���Y���Ȃ��܂��B
�Ⴆ�A
���Y�ƒ���5�N�������n���ꂽ��A
5�N��������
���̌㎀�Y�ɂ���͖̂��ʂł���B
������A���̏ꍇ�͈�ԍ߂̏d�����Y���������
�Ƃ������ƂɂȂ����B
�܂������Y���m�̕����߂ɂȂ����ꍇ�ɂ́A
��Ԓ����̒����ɂ��̒�����2���̂P�𑫂������B
�i�������A�������Ă���߂̍��v�̒������Ȃ��j
��1
����10�N�@����6�N�@����2�N��������A
��ԏd��10�N�ɂ��̔�����5�N�𑫂���15�N���Ȃ��B
�i������5�N�͑��̒����̍��v8�N�ȉ��Ȃ̂łn�j�j
��2
����20�N�@����6�N�@�����Q�N�Ȃ�A
20�N�ɂ��̔���10�N�𑫂���30�N�Ƃ��������Ƃ��낾��
������10�N�͑��̒����̍��v8�N���Ă���̂Ń_���B
����Ē���28�N�ƂȂ�B
�ƍ߂̕s�����A�Y�̌���
�u�Y�@�̊�{�I�Ȃ����v�̃y�[�W�ł�����悤�ɁA�����ȍs�ׂ�ӔC�\�͂�������ΌY���Ə����ꂽ��A
�y���Ȃ����肵�܂��B
����ɂ��ďЉ�܂��B
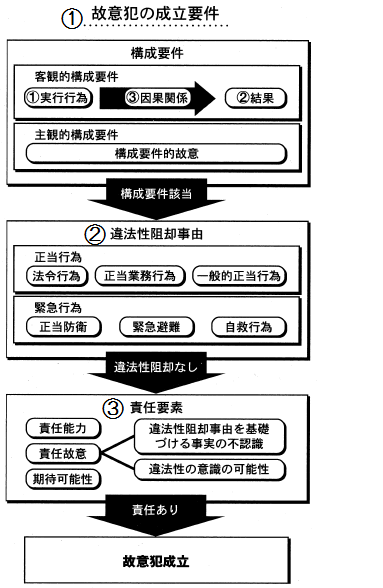
���̐}�̇A�ƇB�ɂ��Đ������܂��B
�ꍇ�ɂ���ẮA
�߂ɋK�肳��Ă���s�ׂ��s���Ă��A
�ƍ߂ɂȂ�Ȃ��ꍇ��A�Y�����Ƃ����ꍇ������܂��B
�������̐}�̇A�̂��������Ƃ��ł��B
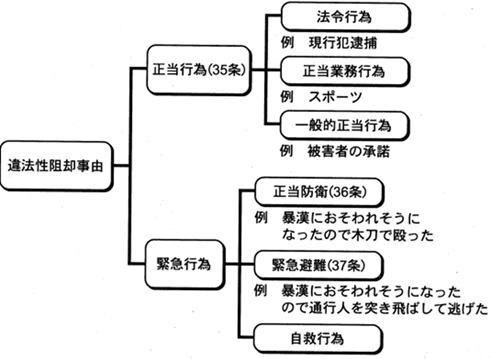
���������ꍇ����@�����j�p�i�����Ȃ�j�Ɣ��f����܂��B
�������A������l�����Ȃ���Έ�@�őߕ߂���܂��B
������l���������ʁA��@���������Ȃ�Ƃ������Ƃł��B
�E�@�ߍs��
�Y���i�ז@�Ɋ�Â��čs���ߕ߂�
�Y�@��31�͂��ߕߋy�ъċւ̍��ɂȂ�܂���B
�E�����Ɩ��s��
�����ȋƖ��ɂ��s�ׂ͔����܂���B
1.�͎m��{�N�T�[������������ĉ����������s�ׁi���Q��\�s�ɂȂ��j
2.���Z���i����@�ɏ]���������Ȑ敨����i�q���߂ɂȂ�Ȃ��j
3.��t����܂𓊗^������O�Ȏ�p�������Ȃ��s�ׁi���Q�ɂȂ�Ȃ��j
4.�Y���������Y�����s����s�ׁi�E�l�߂ɂȂ�Ȃ��j
5.�ƍߎ҂�����ɓ������݁A�q�t�����������܂�����A
�@�x�@�Ɏ������s�ׁi�ߋ��ɔ��Ⴀ��j
�i�q����Ƃ��Đ����Ɩ��s�ׂƂ݂Ȃ���Ɛl�����E�B���߂ɂȂ�Ȃ��j
�ȂǁB
�E��ʓI�����s��
��Q�ґ�������̍s�ׂ�F�߂����͔ƍ߂ł͂Ȃ��Ȃ�B
�Ⴆ�A�F�B���Ƃɏ������ꂽ���A����͏Z���N���߂ł͂Ȃ��B
�w�ւ𓐂܂ꂽ���A
�u����͎��������ɂ���Ă�������̂��v
�ƔF�߂�����̑��^�Ɠ����B
�������A�{�l������̍s�ׂ�F�߂Ă��A
�ƍ߂ɂȂ��Ă��܂����̂�����B
�Ⴆ�A�����킢���Ȃǂ̓_���B
�������ꂽ�l��
�u���肪�C�P�������������狖����v
�Ƒ���̍s�ׂ�F�߂Ă��A
����͋����킢���ɂȂ��Ă��܂��B
�E�����h�q
�����悤�̂Ȃ��N�Q�ɑ��āA
�����̌�������邽�߂ɖh�q�����s�ׂ͔����܂���B
�x���z�����h�q�s�ׂ͔������܂����A
�ʏ�̌Y��肩�͌��Ƃ���܂��B
����ꂽ������{���Ő�������Ă̂�
�N���ǂ����Ă��x���z���Ă܂��̂ŁA
���������͔̂������܂��B
���܂��đ�������ĉ��点�Ă���A
������������s�ׂ�
��������̂ɔ����Ȃ������̂�
�����h�q�ɂȂ�܂���B

���̏ꍇ�A�_�b�V���œ�����Δ�������̂ŁA
���̏�ԂŐ�ɑ���ɉ���ꂽ����ƌ�����
����Ԃ��Ă������h�q�͔F�߂��܂���B
�����A���_���牣�荇���ɂȂ��Ă�
��o���ʼn������ق��͐����h�q�ɂȂ�Ȃ��B
���荇���ɂȂ�O�����킩���Ă�̂�
�����Ȃ����Ă̂͂��������B
����͂����̌��܁B
���������Q��\�s�Ƃ��ōق����B
�}���s�����Ă̂́A�����Ȃ艣��ꂽ�Ƃ��B
�����h�q�́A�s���ɑ��Ă����������̏�Ԃ������܂��B
�E�ً}���
�����̊�@
�D���]�����A�C�ɓ����o����A�����킪1��������������
���̐l����D���Đ������т��B���̐l�͂��ڂ�Ď��B
���Y�̊�@
100���~�̂��̂������邽�߂�10���~�̂��̂�j���B
���������ً}�Ŕ���Ƃ��͍߂ɖ���Ȃ����A
�Y�����y�����ꍇ������܂��B
���ɂ��Ⴆ�A
�E�l�S�ɒǂ�ꂽ���ɒʍs�l�Ɗp�ŏo���킵��
�˂�����Ă����킹���B
�ʍs�l�ɑ��Ă��Ȃ���
���Q��\�s�̍\���v�������Ă��܂��B
�������A����ً͋}��ނ����Ȃ���
���邽�߂ɍs�����s�ׂƂ���
��@�����j�p����܂��B
�ً}���́A
�ǂ������������Ƃ����邽�߂ɂ���Ă�킯����Ȃ��A
���ɑ��Đ��̏�Ԃ������܂��B
�ǂ����������̂ɕK���Ȃ�ł��B
�����܂ł�
�u��@���������Ȃ�v�̂�
�Y�����y����邩�Ə������p�^�[���ɂ���
�������Ă��܂����B
���������
�u��@�������邪�A�ӔC�\�͂������v�̂�
���y����邩�Ə������p�^�[���ɂ��Đ������܂��B
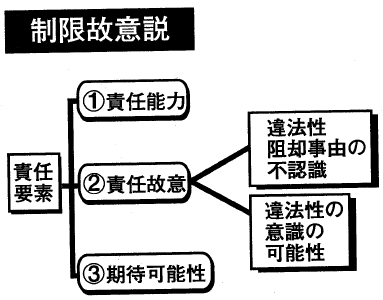
�@�̐ӔC�\�͂������҂́A
�Y�@�ł͈ȉ��̐l���K�肵�Ă܂��B
�S�_�r���ҁi39��1���j���ӔC���\��
�S�_�Վ�i�������Ⴍ�j�ҁi39��2���j������ӔC�\�́i�ӔC�\�͂͏�������j
�Y�������N�i41���j���ӔC���\��
�E�S�_�r��
�S�_�r���҂̍s�ׂ́A�����Ȃ��B
�j���[�X�Ƃ����ĂĂ����Əo�Ă��錾�t�ł��B
�ƍߎ҂ƕٌ�m���b�������āA�Ȃ�Ƃ��Y���y�����悤�Ƃ���Ƃ���
�S�_�r����F�߂Ă��炨���Ƃ���p�^�[���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�E�ӔC�N��
14�Ζ����͔����܂���B14�Ζ������Y�������N�ƌ����܂��B
���@��20�Ζ����������N�Ƃ͈Ⴂ�܂��B
�������Ȃ������肽������Ƃ������o�J�����܂����A
�Y�@���K�p����Ȃ������ŁA���N�@���K�p�ɂȂ�܂��B
�Y�@�ŏd���Y���Ȃ������A
���N�ɂ͂ނ��닳����s�����������̂ł́H
�Ƃ����l���ŌY�@���班�N�@���h�����܂����B
�܂�A���N�@�ɏ]���ċ����I�ɕ��������܂��B
14�Έȏ�20�Ζ��������N�@�̓K�p��
�Y���y������Ƃ�����܂����A
��{�I�ɂ͌Y�@�̏����ɏ]�����ƂɂȂ�܂��B
��
�ƍ߂�Ƃ�������18�Ζ����ł��������N�̗ʌY�Ɋւ��āA
���Y�������ď��f���ׂ��ꍇ�͖����Y�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���B
�����āA�����Y�������ď��f���ׂ��ꍇ�ł��A
10�N�ȏ�15�N�ȉ��̗L���Y�ɂł���Ƃ���B
���̂悤�ɁA�Y�@�Ō��܂����Y�ɂ���
���N�@�Ōy�����������B
�E�̈�
�߂�Ƃ��ӎv���Ȃ��s�ׂ͔����܂���B
�̈ӂ����邩�ǂ����͂��̐l�̍s���ɂ����
�q�ϓI�ɔ��f����܂��B
���̑��Y�̏d���ɊW���邱��
�E�����{���@�ւ�������O�ɖ����o�邱�ƁB
�x�@�͌Y�����y�ł���B
���y�ł���̂ł����āA
���ޗʂ̗]�n��������Ό��y���Ȃ����Ƃ�����B
�E���ޗ�
���ޗʂ�����Ƃ��͌��y����B
�Ⴆ�A
������������E���ĕی����Ȃ���
���q�̕a�C������������ł��܂��Ƃ��A
���������ꍇ�͏��ޗʂ�����Ǝv���܂��B
�E������
�ƍ߂����s�ɏI������҂́A
�x�@�̔��f�Ō��y����܂��B
����Ɏ��Ȃ̈ӎv��
�ƍ߂𒆎~�����ꍇ�́A
�x�@�̔��f�Ō��y��Ə��ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B
�����ɂ���
�i�Y�̎����j��O�\��� �@�Y�̌��n�������҂́A�����ɂ�肻�̎��s�̖Ə���B
�Y�������n���ꂽ���̓�����A
�����̓����𐔂��܂��B
�����𐔂��Ĉȉ��̊��Ԃɓ��B������A
�����ɂ���ČY�̎��s���Ȃ��Ȃ�܂��B�@
�E���Y��30�N
�E���������A�Ł�20�N
�E10�N�ȏ�̒����A�Ł�15�N
�E3�`9�N�̒����A�Ł�10�N
�E3�N�����̒����A�Ł�5�N
�E������3�N
�E�S���A�ȗ��A�v����1�N
�}�ɂ���ƁA
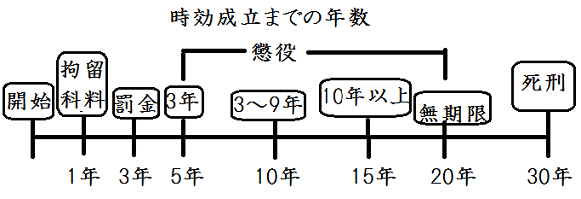
�����͌x�@�ɍS������Ă��鎞�Ԃ�
�N�����J�E���g���܂���B
�ȏオ�A
�Y�̏d����A
�Y���y�����ꂽ��A�Ə����ꂽ�肷����e�ł��B
�X�|���T�[�h�����N
�Y�@�̊�{�I�Ȃ���
�Y�̏d���̍l����
���Ƃɑ����
�Љ�ɑ����
�l�ɑ����
���Y��N�Q�����
�ٔ��T���̎d��
�o�i�[�X�y�[�X
�X�|���T�[�h�����N
�Ɨ��؎q�m�Ƃ��āA
�؎q�̍H�[�𗧂��グ�܂����B

�؎q�H�[�@⼌��i�����j
�֘A�T�C�g
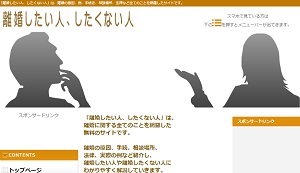
�����������l�A�������Ȃ��l
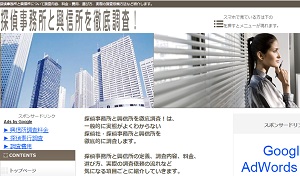
�T�㎖�����Ƌ��M����O�꒲���I