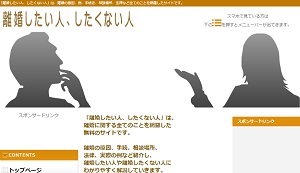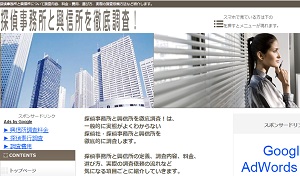労働関係調整法
労働関係調整法
無料法律解説サイト トップページ>労働法>労働関係調整法労働三法という基本の法律の1つである
労働関係調整法について解説していきます。
労働関係調整法は、
「労働組合法」を補助する形の法律です。
労働組合と使用者で話の折り合いがつかない時は
ストライキになりますが、
ぽんぽんストライキが起こってしまうのも問題なので、
争議行為を抑制して、平和な解決を促す法律です。
条文は1条〜43条で短めです。
さらに内容を短くしたりしているので、
普通に条文を読むより読みやすいと思います。
公益事業とは、
公共の利益となるインフラに近い業種で以下のものです。
一 運輸事業
二 郵便、電気通信事業
三 水道、電気、ガスの供給事業
四 医療事業
公益事業に努めている人が
突然ストライキを起こすと
社会に与える損害が計りしれないので、
これらの業種でストライキを行うには
他の職種より様々な規制があります。
スポンサードリンク
第1章 総 則 (第1条〜第9条)
第一条この法律は、労働組合法 と組み合わさって労働関係の公正な調整を図り、
労働争議を予防し、又は解決して、
産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする。
第二条
常に労働関係の調整をするための正規の機関の設置、
運営の事項を労働協約に定めるように特に努力しなければならない。、
また、労働争議が発生したときは、
誠意をもって自主的にこれを解決するように特に努力しなければならない。
第三条
労働関係に関する主張が一致しない場合、
当事者間で自主調整することの助力を政府は与え、
争議行為の防止に努めなければならない。
第四条
この法律は、当事者の労働条件の不一致を調整することを妨げるものでない。
労働関係の当事者が、かかる努力をする責務を免除するものではない。
第五条
この法律によって労働関係の調整をすることになった場合、
当事者と労働委員会は、最善の方法で調整処理を図らなければならない。
第六条
労働争議とは、労働関係での主張が一致しないために争議行為が発生している状態を言う。
または発生する恐れがある状態を言う。
第七条
争議行為とは業務の正常な運営を阻害するもので主張を押し通すための行為。
労働者だけではなく、使用者側も争議行為に対抗するために
建物を閉鎖したりします。
建物を閉鎖し、無期限に労働をさせないことで
給料を断って相手に泣きつかせようということです。
労働者
同盟罷業(ストライキ)、怠業(サボタージュ)が争議行為としてある。
使用者
作業所閉鎖(ロックアウト):閉鎖して働かせないことで賃金を払わない。
ロックアウトの正等要件
・組合側による争議行為が存在すること
・使用者が著しい損害を受けること
・労使間の均衡を回復するための対抗的防衛手段であること
したがって、労働者側からの圧力がなく、
単に賃金負担を軽減するなどの意図で行われたロックアウトは、認められません。
逆に、部分スト・指名スト・巡回スト・波状スト・サボタージュ等は、
労働者側に発生する損失の程度は比較的少ないのに対し、
使用者側に生じる損失は大きいため、
この種の争議行為に対してもロックアウトは有効であり、
正当だと解されています。
(ただし、部分ストをした労働組合員しか争議行為してないので全部をしめだしても、ダメ
争議行為による損害を緩和するために行う
対抗的・防御的ロックアウトには正当性が認められますが、
争議行為を行っていない段階で行う
先制的ロックアウトや、使用者が自己の要求を貫徹する圧力手段として行う
攻撃的ロックアウトには正当性が認められません。
第九条
争議行為が発生したときは当事者は直ちにその旨を
労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない。
第2章から第4章は争議行為の解決方法について書かれています。
第2章→あっせん
第3章→調停
第4章→仲裁
第2章 斡 旋(第10条〜第16条)
斡旋(あっせん)は、労働委員会の会長が指名するあっせん員が当事者の間に立って双方の主張を確認し、
話し合いを取りもつことにより労働争議を解決に導く調整方法で、
現在、3つの調整制度の中で、このあっせんが最も多く利用されています。
第十条
労働委員会は、斡旋員候補者を委嘱し、その名簿を作成して置かなければならない。
第十一条
斡旋員候補者は、争議解決の援助ができる者でなければならない。
その労働委員会の管轄区域内に住んでいなくてもよい。
第十二条
争議発生時に労働委員会の会長は当事者の双方、
または一方の申請、または会長の職権で斡旋員名簿の中から、斡旋員を指名する。
第十三条
斡旋員は双方の主張の要点を確め、事件解決に努めなければならない。
第十四条
斡旋員が、自分では事件解決できないと感じた時、
その事件から手を引き、事件の要点を労働委員会に報告しなければならない。
第十四条の二
斡旋員は、政令で定めるところにより、
その職務を行うための費用の弁償を受けることができる。
第十五条
斡旋員候補者に関する事項は、この章に定めるほか、命令でこれを定める。
第十六条
この章の規定は、争議の当事者が、双方の合意、
または労働協約により、別の斡旋方法によって
事件解決を図ることを妨げるものではない。
第3章 調 停(第17条〜第28条)
調停とは、労働委員会が対立する双方の間に立って話を聞いてあげることです。
第4章の仲裁は和解しているのに対して、
こっちは和解はしてないが、間に立って話を聞いてもらいたい、
という状態です。
第十八条
労働委員会は、次のいずれかの場合、調停を行う。
一 当事者の双方から、労働委員会に調停申請されたとき。
二 当事者の双方か一方から、労働協約に基づいて、労働委員会に調停申請されたとき。
第十九条
労働委員会による争議調停は使用者、労働者、公益者を代表する
各々の調停委員から成る調停委員会を設け、これによって行う。
第二十条
調停委員会内では、使用者代表と労働者代表は、
同数の調停委員でなければならない。
第二十二条
調停委員会に委員長を置く。
委員長は公益者代表委員の中から選挙する。
第二十三条
調停委員会は、委員長が招集し、出席者の過半数で有効となる。
調停委員会は、使用者代表と労働者代表が出席しなければ、会議を開くことはできない。
第二十四条
調停委員会は、期日を定めて、
当事者の出頭を求め、その意見を集めなければならない。
第二十五条
調停をする場合、調停委員会は、関係者以外の出席を禁止できる。
第4章 仲 裁(第29条〜第35条)
労働委員会に両社から仲裁の申請があったときに仲裁の書面を書いて争いをおしまいにします。
書いた書面は労働協約と同じ効果を持ち、
就業規則より強い効力を持ちます。
第二十九条
労働組合法第二十条 の規定による労働委員会による労働争議の仲裁は、
この章の定めるところによる。
第三十条
労働委員会は当事者双方から仲裁申請されたとき、仲裁を行う。
また、労働協約に、労働委員会の仲裁申請をする旨がある場合、
当事者の双方または一方から仲裁の申請がなされたとき、仲裁を行う。
第三十一条
労働委員会による争議仲裁は、
仲裁委員3人から成る仲裁委員会を設け、これによって行う。
第三十二条
仲裁をする場合、仲裁委員会は当事者及び参考人以外の出席を禁止できる。
第三十三条
仲裁裁定は、書面に作成してこれを行う。
その書面には効力発生の期日も記さなければならない。
第三十四条
仲裁裁定は、労働協約と同一の効力を有する。
第四十三条
調停、仲裁をする場合、公正な議事進行を妨げる者に
調停委員会の委員長又は仲裁委員会の委員長は、
退場を命ずることができる。
労働関係調整法はこれで以上です。
ただ現実に起きる争議というのは条文では
カバーしきれないほど何かしらの問題を抱えているので、
ここの条文を知ったうえで弁護士に相談してみるといいと思います。
スポンサードリンク
労働三法
労働基準法
労働組合法
労働関係調整法
派生した法律
労働安全衛生法
労働契約法
最低賃金法
パートタイム労働法
高齢者雇用安定法
育児介護休業法
男女雇用機会均等法
公益通報者保護法
障害者雇用促進法
労働者災害補償保険法
雇用保険法