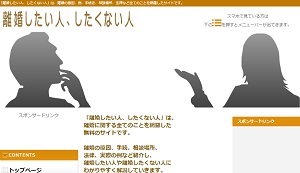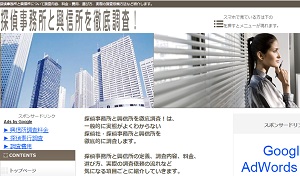保証人
保証人に関する法律
無料法律解説サイト トップページ>民法>保証人に関する法律>保証人連帯保証人ではなく、
通常の保証人について説明します。
保証人になるには、
・行為能力者(未成年、成年被後見人では無いなど)
・弁済能力がある
の2つが必要とされています。
行為能力者がのちに事故で、
自分で意思決定をできないなど
誰かに意思決定を任せる成年被後見人になった場合でも、
保証人としての要件を満たします。
しかし、もし前提の弁済能力が途中で無いとみなされた場合、
債権者は債務者に別の保証人になってくれる人を
探すように請求することができます。
もし、別の保証人を立てられない場合は、
抵当権などの別の担保を供することができる。
スポンサードリンク
保証は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、
その履行をする責任を負います。
保証の契約はかなり危険なため、
口頭での契約を禁じています。
元々は書面で結んだ契約でしか効力を生じませんでしたが、
近年の現状に合わせてパソコン上での契約も
書面と同じ効力を持つようになりました。
保証人は、
・主たる債務に関する利息
・違約金
・損害賠償
・その他その債務によって発生した費用
を全て支払う義務があります。
ただし、それらの付随して発生した費用について
いくらまで払うという契約を結ぶこともできます。
限度額をあらかじめ決めておくということ。
肩代わりをする人が主たる債務者より重い責任を負うのは妥当でないため、
もし、オーバーした場合は主たる債務者と同じレベルまで減縮されます。
もし、元の債務者がまだ払えるのに
保証人の自分のところに取り立てが来たら、
「まだ元の債務者の方から取り立ててくれよ」
と請求することができます。
細かいルールもありますが、
大まかに重要なルールを抜き出すとこんな感じです。
あとの実状にあわせた細かい話は、
弁護士の先生に聞いてみて下さい。
スポンサードリンク
連帯保証人
保証人
根保証