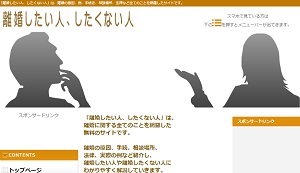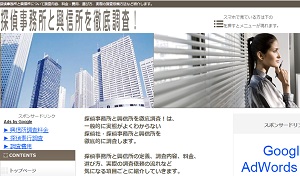離婚の法律
離婚の法律
無料法律解説サイト トップページ>民法>離婚や親権に関する法律>離婚の法律離婚に関しては
お互いに話し合って決める「協議離婚」と、
話し合いにならないので
裁判所に決めてもらう「裁判離婚」があります。
スポンサードリンク
協議離婚
(協議上の離婚)第七百六十三条 夫婦は、その協議で、離婚できる。
協議によって「離婚届けを提出することに合意」することです。
離婚の真意は問われず、届けをだすか出さないかだけで判断されます。
例えば、
借金逃れという本当の目的があって
仮装離婚・一時的に離婚する場合であっても
離婚は有効です。(過去に判例あり)
詐欺または強迫によって離婚した場合は婚姻の時と同じく、
「その離婚は無効です」って主張をすれば、無効になる。
3か月の間に主張しなければ、詐欺や強迫による離婚でも有効になる。
裁判離婚
夫か妻は以下の内容にいずれかに該当すれば、離婚の訴えを裁判所に提起できます。
1.配偶者に不貞行為があったとき
不貞行為、いわゆる浮気のこと。
判例では自分の意思で
配偶者以外の者と性的関係を結ぶこととしている。
強姦を繰り返した旦那は自分の意思で強姦しているので、
離婚の原因になる(最高裁判例)
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
悪意の遺棄とは、
積極的な意思で夫婦の共同生活を行わないことです。
同居しないことや協力・扶助義務違反のこと。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
ただし、すぐに離婚すると精神病になっている側が著しく不利になるので、
今後の療養日程や生活の補助など具体的対策を行い、
それで精神病の方がなんとかやっていけると裁判所が判断したら
離婚を認めるとしている(最高裁 昭和45年11月24日)
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
性格の不一致、
親族との不仲(嫁姑関係など)、
難病(アルツハイマー)、
過度の宗教活動
など過去の判例で認められています。
不貞行為をした側(浮気をした方)が
「離婚したい」と請求することは認められるのか?
昔は認められなかったけど、
昭和62年9月2日の最高裁判例で初めてそういう請求が認められた。
1.夫婦の別居が当事者の同居期間と比べ、相当長いこと。
2.未成熟の子がいないこと。(高校生は成熟とした判例がある)
3.離婚によりどちらかが精神的・社会的・経済的に過酷な状態に置かれないこと。
の3つを要件にそういう請求が認められた。
離婚後の子供の養育費
子の監護費用(養育費)はどちらがいくらどちらに払うか、監護権者じゃない方はどのように会えるか(面接交渉)など
両者で話し合って決めます。
そもそも協議できないくらい拒絶されている状態でも
家庭裁判所に頼んで審判によってこれらの事項を決定できます。
両者の協議が決まっても、家庭裁判所は
「養育費は支払いなさい」とか
「1ヶ月に1回は最低会わせてあげなさい」とか
子の監護に必要な処分を命じることができる。
ここで言っているのは子の養育費の問題であって、
親権の問題ではありません。
例えば、子の親権が妻だとしても、養育費は夫が払うパターンもありますよね。
「養育費を払うから親権がある」ということではないことを理解しておいて下さい。
養育費に関しては、
基本的に収入が安定している夫の方が払うパターンが多いと思います。
それに漬けこんで、養育費を奪う目的で親権を取ろうとする妻がいます。
妻の不貞行為で離婚した場合、
妻には子を育てる意思が無いと推定できます。
それなのに親権を請求してきた場合は、
子供の養育費を使って遊びに使うことが予想できますので、
夫の人は子供の未来のためにも親権は必ず手に入れて下さい。
離婚後の財産分与
財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して蓄積した財産を精算すること
を言います。
婚姻中に協力して蓄積した財産なので、
「夫婦の財産について」で説明した通り、
婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は
それぞれの特有の財産として分割しないので覚えておいて下さい。
財産の分け方は話し合いで決めますが、
話し合いで決まらない場合や、
相手が嫌いすぎて話し合いにも応じてくれない場合は
家庭裁判所に財産を分けてもらうようにお願いすることができます。
家庭裁判所にお願いした場合は、
離婚後の経済的弱者(妻の場合が多い)に対する扶養料や、
離婚について有責である配偶者の慰謝料も考慮した金額で
財産分与の金額を決定してくれます。
慰謝料込みの金額で財産分与してくれますが、
さらに別に711条精神的苦痛による損害賠償を相手方にしても構いません。
ただし、慰謝料込みで財産分与されているので、
損害賠償をもらえるとしても、その金額が考慮された金額になります。
協議離婚するときは、
親は話し合って一方を親権者と決めないといけません。
裁判離婚は、判決で親のどちらかを親権者が決まります。
お腹に子供がいる場合は母親が親権者となるが、
話し合いで父親を親権者にすることもできます。
非嫡出子の場合も話し合いの上で父親を親権者にできます。
この離婚の項目とつながっている内容なので、
「親権」も確認してみて下さい。
スポンサードリンク
婚姻の基本的なこと
婚姻の効力
夫婦の財産について
離婚の法律
親権
養子